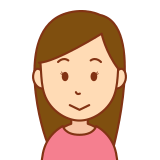
こどもが朝になかなか起きられない、めまいがする、頭痛、腹痛がすると言って学校を休むんですけど・・・病気でしょうか?
このようなご相談は、小学校半ばくらいのお子さんを持つ親御さんから受けることが多いです。
特にコロナ感染症後から増えた印象があります。
この他の疾患(貧血や不整脈など)を否定した上でのお話しにはなりますが、
体の中で起きていること、自宅でできる対応、病院受診の目安などについてお話ししますね。
起立性調節障害 (Orthostatic Dysregulation: OD) とは?
自律神経の働きが乱れることで、体位の変化に適切に血圧や心拍数が調節できず、朝起きて立ち上がる際などにさまざまな症状が出る疾患です。

特に思春期の子どもに多く、日常生活や学校生活に支障をきたすことが多いです。
学校を休みがちになり、怠けているの?と思われがちですが、本人は辛いはずです。
主な症状
- 立ちくらみやめまい(特に朝や立ち上がったとき)
- 全身倦怠感
- 頭痛(特に午前中に強い)
- 動悸
- 食欲不振や腹痛
- 朝起きられない
- 集中力の低下、勉強や学校生活に支障が出る

上記のような症状があったら、ODの可能性を考え、検査を受けましょう。
診断方法
- 問診
子ども本人や家族からの症状の聞き取りが重要です。朝起きられない、学校を欠席しがちなどの生活状況も確認します。睡眠時間や生活パターンなども詳しく聞きます。 - 身体所見
身長・体重測定や心音確認などの一般的な診察。 - 体位変化試験(立位試験やチルトテストなど)
- 目的: 体位変化による心拍数や血圧の変化を測定。
- 方法: 仰臥位で10分以上休んだ後、立位またはTILT試験台での測定を行い、心拍数・血圧の変化を記録。
- 他の疾患の除外
- 貧血、甲状腺異常、心疾患(不整脈など)を血液検査や心電図で確認。
- 心拍数の変化
起立時に心拍数が急上昇するかを確認。これが顕著であれば「体位性頻脈症候群(POTS)」の可能性も考えられます。

体が思うようについていかず、一番つらいのはお子さんです。
ODは治療法がある病気ですので、ぜひ受診されて検査を受けてくださいね。
似たような症状は貧血でも起こりえますね。
貧血の記事もよければ参考にしてみてくださいね。

治療方法
- 規則正しい生活習慣: 毎日同じ時間に起床・就寝。睡眠の質を改善する。
- 塩分と水分の積極的な摂取: 自律神経を安定させ、血圧を保つ。
- 適度な運動: 下肢の筋力を鍛え、血液の循環を改善。
- 入浴の注意: 長風呂や熱いお湯を避ける。
- 着圧ソックスの使用:患者さんにもおすすめしています。
血圧を上げるお薬や自律神経の働きを整えるお薬を使うことがあります。
不安を減らし、心理的ストレスを軽くする、自己肯定感が低下する場合、心理的ケアやカウンセリングも必要。
怠けなどではないこと、本人が一番つらいことを周囲で理解する必要があります。
登校できない子どもには、短時間登校やオンライン学習の導入を検討。
長期的な見通し
- 思春期に多い疾患ですが、成長とともに症状が軽快するケースが多い。
- 適切なサポートを受けることで、生活の質を改善できる可能性が高い。
- 薬物治療を行っても改善が見られないなどは、ODだけではない可能性がある。
- 子どもの「だるさ」や「起きられない」ことを怠けと捉えず、医学的な原因がある可能性を理解し、検査を受けましょう。
- 医師と協力しながら、無理のない範囲での学校生活や家庭でのケアを心がけることが大切。
- 成長とともに軽快する可能性が高いので、お子さんが過剰に不安にならないようにします。
小学校半ばくらいになり、今まで毎日学校に行けていたのに、どうして?と不安になりますよね。
診療していても、年々ODのお子さんは増えている印象です。

では、なんでこんなに増えたのでしょう??
特に思春期の子どもたちの中で多く見られるこの症状は、学校生活や社会環境の変化が影響している可能性があります。
- 昔は「怠け」や「精神的な弱さ」と誤解されることも多かったOD、医療機関や教育機関での認知度が高まり、正確な診断を受けられるケースが増えている。
- 専門的な検査(チルト試験など)や小児科医の知識が広がったことで、より多くの子どもが見逃されずに済むようになった。
- スマートフォンやタブレットの使用増加により、就寝時間が遅くなる子どもが多い。
- 塾や習い事の低年齢化により、帰宅時間、就寝時間が遅れる。
- 親の共働きが増え、帰宅時間、就寝時間が遅れる。
- 家庭でのゲームや動画視聴が増え、体を動かす機会が減った。
- 下肢の筋力低下や血流不全が、自律神経の乱れに繋がる。
- 朝食を摂取しない、夕食が遅いなどにより、自律神経の乱れが生じます。
- 学業のプレッシャーや進学競争が激化しており、子どもたちに大きなストレスがかかる。
- 学校や家庭での人間関係の問題、いじめ、SNSでのストレスもかかる。
どれもこれも、すぐには解決できないことばかりですが、こういう疾患があることを認識するのは大切ですね。わたしも仕事の都合上、こどもの就寝時間が遅くなりがちです。
大人も子どもも忙しい毎日。一緒に頑張りましょうね。




コメント