お子さんの指しゃぶり、赤ちゃんらしくてとっても可愛らしいですよね。
でもいつまでもやっているけど、大丈夫?今後に影響はないの?そんな疑問にお答えします。
乳幼児が安心感を得たり、自己安慰行動として行う一般的な習慣。
多くの場合、成長とともに自然にやめるものですが、長期間続く場合や、何かしらの影響がある場合は注意が必要です。
指しゃぶりの年齢による特徴
- 生後数ヶ月~2歳頃まで:正常な発達過程の一部として広く見られる。安心感を得るための自然な行動。
- 2~4歳頃:多くの子どもが自然に指しゃぶりをやめる。
- 5歳以降:歯並びや言語発達、心理的影響に関与する場合があるため、継続している場合は観察が必要。
- 生後数ヶ月~2歳頃まで:正常な発達過程の一部として広く見られる。安心感を得るための自然な行動。
- 2~4歳頃:多くの子どもが自然に指しゃぶりをやめる時期。
- 5歳以降:歯並びや言語発達、心理的影響に関与する場合があるため、継続している場合は注意して観察が必要。

こどもの精神安定の役割をしているので、無理にやめさせる必要はないですが、影響が出てきている場合にはやめさせることも考えないといけませんね。
やめさせるべき基準
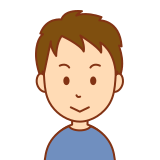
ではどんな時にやめさせればよいですか?
- 長期的な指しゃぶりは、上顎や前歯の位置に影響を与え、不正咬合(出っ歯など)を引き起こす可能性があります。
- 特に、永久歯が生え始める5~6歳以降では注意。
指しゃぶりが頻繁で、発話に影響を与えている場合。
指しゃぶりにより、指の皮膚が荒れる、爪が変形するなどの身体的な問題が起きている場合。
強い不安やストレスのサインとして指しゃぶりが行われていることもあります。その背景にある原因を探ってあげないと根本的な解決には至りません。
やめさせる方法

無理にやめさせると逆効果になることもあるため、子どもの不安な気持ちに寄り添いながら、ゆっくり進めます。
- 他の触れるものを与える
- 子どもが安心できる環境を整え、指しゃぶり以外の安心できるもの(ぬいぐるみ、タオルなど)を提供する。
- 具体的な働きかけ
- 4~5歳以降で継続している場合、歯科医や小児科医の助言を受けながら対策を取る。
- 指に苦味のある薬を塗る、絆創膏を貼るなど、物理的に触れるのを防ぐ方法を使うことも。
- 褒めるアプローチ
- 指しゃぶりをしなかった時間を褒めるなど、前向きな方法を試します。
- ストレス要因の解消
- 生活環境や親子関係の見直しを行い、指しゃぶりの原因を取り除く。
上のような方法でもなかなかやめられない、皮ふも荒れてきている、年齢も上がってきて見た目にも恥ずかしいなど、
そのような時には苦いマニキュアなどに頼る、矯正器具に頼るなどもよいと思います。

指しゃぶりで親指がぼろぼろ、細菌感染を繰り返していたお子さん、こちらを使用してみましょう、とお話しし、実際に使用してもらいました。
医療法人が監修している点、お口に入れても安心の植物由来の苦み成分であることがポイントです。

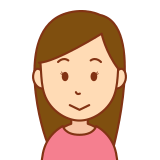
最初の2日ほどは心のよりどころがなくなったようで不安そうだったけれど、それ以降は指しゃぶりをすっかり忘れてしまったようです。指の感染もよくなりました。
こういう症例には、お薬に頼って無理にやめさせることも必要です。
まとめ
赤ちゃんの指しゃぶり、とっても可愛らしいのですが、やめさせるべき基準に当てはまる時には
やめさせる方法を考える必要があります。自分で納得して、自然にやめるのが一番ですが、なかなか
そううまくいかないことも事実です。そんな時には上記のものを試してもよいでしょうし、小児科医や
小児歯科医に相談するようにしてくださいね。




コメント